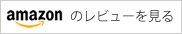「職業としての小説家」の名言集

職業としての小説家
出版社:スイッチパブリッシング
単行本発売日:2015/9/10
単行本:313ページ
P.37:「小説家になった頃」
言葉には確かな力がある。しかしその力は正しいものでなくてはならない。少なくとも公正なものでなくてはならない。言葉が一人歩きをしてしまってはならない。
P.42:「小説家になった頃」
広島の先発ピッチャーはたぶん「高橋(里)」だったと思います。ヤクルトの先発は安田でした。一回の裏、高橋(里)が第一球を投げると、ヒルトンはそれをレフトにきれいにはじき返し、二塁打にしました。バットがボールに当たる小気味良い音が、神宮球場に響き渡りました。ぱらぱらというまばらな拍手がまわりから起こりました。僕はそのときに、何の脈絡もなく何の根拠もなく、ふとこう思ったのです。「そうだ、僕にも小説が書けるかもしれない」と。
P.46:「小説家になった頃」
僕がそのときに発見したのは、たとえ言葉や表現の数が限られていても、それを効果的に組み合わせることができれば、そのコンビネーションの持って行き方によって、感情表現・意思表現はけっこううまくできるものなのだということでした。要するに「何もむずかしい言葉を並べなくてもいいんだ」「人を感心させるような美しい表現をしなくてもいいんだ」ということです。
P.53:「小説家になった頃」
「さあ、これから何を書こうか」と考えを巡らせます。そのときは本当に幸福です。正直言って、ものを書くことを苦痛だと感じたことは一度もありません。というか、もし楽しくないのなら、そもそも小説を書く意味なんてないだろうと考えています。
P.68:「文学賞について」
後世に残るのは作品であり、賞ではありません。二年前の芥川賞の受賞作を覚えている人も、三年前のノーベル文学賞の受賞者を覚えている人も、世間にはおそらくそれほど多くはいないはずです。あなたは覚えていますか?しかしひとつの作品が真に優れていれば、しかるべき時の試練を経て、人はいつまでもその作品を記憶にとどめます。
P.124:「さて、何を書けばいいのか?」
僕は楽器を演奏できません。少なくとも人に聞かせられるほどにはできません。でも音楽を演奏したいという気持ちだけは強くあります。だったら音楽を演奏するように文章を書けばいいんだというのが、僕の最初の考えでした。そしてその気持ちは今でもまだそのまま続いています。こうしてキーボードを叩きながら、僕はいつもそこに正しいリズムを求め、相応しい響きと音色を探っています。それは僕の文章にとって、変わることのない大事な要素になっています。
P.130:「さて、何を書けばいいのか?」
もしあなたが小説を書きたいと志しているなら、あたりを注意深く見回してください――というのが今回の僕の話の結論です。世界はつまらなそうに見えて、実に多くの魅力的な、謎めいた原石に満ちています。小説家というのはそれを見出す目を持ち合わせた人々のことです。そしてもうひとつ素晴らしいのは、それらが基本的に無料であるということです。あなたは正しい一対の目さえ備えていれば、それらの貴重な原石をどれでも選び放題、採り放題なのです。
こんな素晴らしい職業って、他にちょっとないと思いませんか?
P.150:「時間を味方につける ―― 長編小説を書くこと」
ここで僕が言いたいのは、どんな文章にだって必ず改良の余地はあるということです。本人がどんなに「よくできた」「完璧だ」と思っても、もっとよくなる可能性はそこにあるのです。
P.157:「時間を味方につける ―― 長編小説を書くこと」
「やるべきことはきちんとやった」という確かな手応えさえあれば、基本的に何も恐れることはありません。あとのことは時間の手にまかせておけばいい。時間を大事に、慎重に、礼儀正しく扱うことはとりもなおさず、時間を味方につけることでもあるのです。女性に対するのと同じことですね。
P.160:「時間を味方につける ―― 長編小説を書くこと」
自分の「実感」を何より信じましょう。たとえまわりがなんと言おうと、そんなことは関係ありません。書き手にとっても、また読み手にとっても、「実感」にまさる基準はどこにもありません。
P.224:「どんな人物を登場させようか?」
小説を書いていて、いちばん楽しいと僕が感じることのひとつは、「なろうと思えば、自分は誰にでもなれるんだ」ということです。
P.232:「どんな人物を登場させようか?」
小説がうまく軌道に乗ってくると、登場人物たちがひとりでに動きだし、ストーリーが勝手に進行し、その結果、小説家はただ目の前で進行していることをそのまま文章に書き写せばいいという、きわめて幸福な状況が現出します。そしてある場合には、そのキャラクターが小説家の手を取って、彼をあるいは彼女を、前もって予想もしなかったような意外な場所に導くことになります。
P.236:「どんな人物を登場させようか?」
『海辺のカフカ』を書いたとき、僕は五十歳を少し過ぎていましたが、主人公を十五歳の少年に設定しました。そして書いているありだ、自分が十五歳の少年であるように感じていました。
P.252:「誰のために書くのか?」
僕が小説かになり、本を定期的に出版するようになって、ひとつ身にしみて学んだ教訓があります。それは「何をどのように書いたところで、結局はどこかで悪く言われるんだ」ということです。